PICK UP
『星のカービィ』シリーズを手がけた石川淳&安藤浩和(HAL研究所)に話を聞く!|キーボード・マガジン 2017年7月号 SUMMERより
Text by キーボード・マガジン編集部
今年25周年を迎える『星のカービィ』シリーズ。キュートなキャラクターが活躍するアクション・ゲームは、音楽のクオリティの高さでも多くの支持を受ける。そのシリーズ最初期から作品を手がけるのが、HAL研究所のサウンド・チームに所属する石川淳と安藤浩和だ。 普段あまり表に出ることのない彼らだが、今回は貴重なインタビューの機会を得ることができた。 カービィの世界を色彩豊かに表現し、プレイヤーたちをワクワクさせるメロディ、 そしてサウンドはどのように作られているのか。山梨にある同社の開発センターにてじっくりと話を伺った。
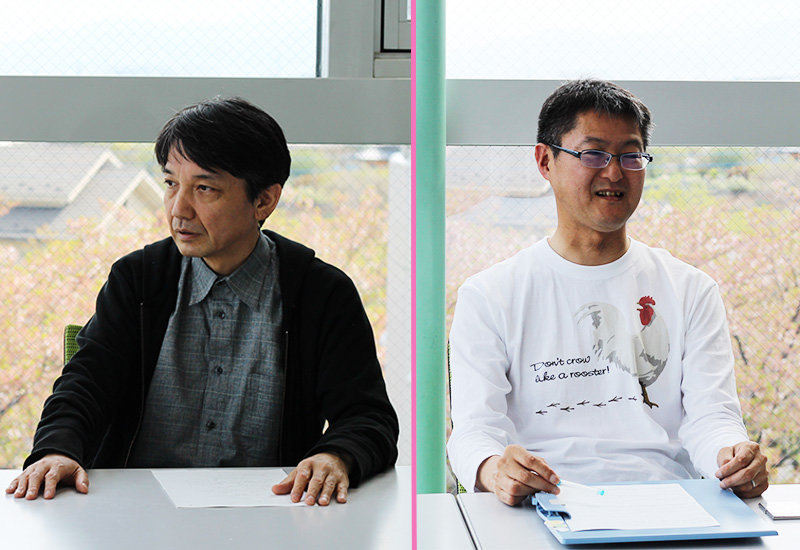
─『星のカービィ』シリーズは今年で25周年を迎えますが、開発されたときはどのような感じだったのでしょうか?
石川 1作目の『星のカービィ』(1992年)は、BGMも効果音も全部私がやっています。あれはゲームボーイだったんですが、ファミコンの開発ツールをそのまま流用して使っていました。ただ、ファミコンのこの音はゲームボーイでは鳴らないというように、ちょっとした違いというか制限はありました。でも、バイオリンではギターの音が出ないって言っても仕方がないのと同じで、ゲームボーイという楽器からゲームボーイの音が出ると考えるしかないわけです。そして、出る音の全責任は私にあった。初代ゲームボーイは、ちょっとでも複雑な和音を鳴らそうとすると、バリバリっと歪んでしまったりするんですね。なので、メロディを中心に作ろうと。どうしたら少ない音でいい曲が作れるのか、ゲームボーイのいろいろなゲームをやってみたりしました。それで、なるべく子供が口ずさめるようなメロディを主体にして、何となくコードを感じさせるようなベースを作って。できたのが「グリーングリーンズ」のメロディ・ラインなんですが、あれは三角波に聴こえますよね。ファミコンには三角波があるんですが、ゲームボーイにはないんです。でも、どうしても三角波が欲しくて。そこで、ゲームボーイは波形メモリーがあるので、三角波っぽい波形を書きました。波形メモリーは、ちょうど2波形分くらいの複雑な波形を書けるので、ふた山書いてあの音ができたんです。いろいろ工夫はしましたが、「グリーングリーンズ」は、『スーパーマリオブラザーズ』や『ゼルダの伝説』のような圧倒的な楽曲とは思っていなかったし、それどころかゲームボーイから出てくる音楽なんて誰も聴いていないだろうとすら当初は思っていて......まさかこんなに聴いてくれている人がいたとは。有難いですね。
─2作目は、先ほどもお話に出てきた『星のカービィ 夢の泉の物語』。これは安藤さんが担当された。
安藤 私は複雑な和音が好きなのでなんとかして使いたいと思いつつも、やっぱり制限がすごく多くて。特に容量の制限は厳しかったので、どんな曲も繰り返しを多用しないとメモリーに入らなかったのですが、それがかえってまとまりのある曲に行き着いたんじゃないかと思います。入社当時は、それほどちゃんとしたものは作れていなかったので、そういう制限があってむしろ良かったです。ハードの進化に伴って、私もまともなものを作れるようになっていったので、うまい具合にここまで来れたのかなって思います。
石川 制限がなくなると自由になるのかという点については、ずっとジレンマを感じています。要するに便利になるほど不自由になる側面は必ずあって、そのテーマはこれからも残るんだろうと思います。私はモジュラー・シンセが大好きですが、ゲーム制作には使いません。モジュラー・シンセはどこまでも自由ですが、同時に不便ですよね。何かできなかったものをできるようにしたら、こっちができなくなったっていう、自由さと不便さの対決がどこまでいっても付いて回るっていうか。それが実感としてあります。不便だからなんとかしたいと改善してきて今があるから仕方ないと思いますし、今後もずっと悩みながらやっていくんだろうと思います。
─『星のカービィ』シリーズは、共作されることも多いですが、この曲とこの曲はどっちがやって、といった役割分担のようなものはどう決めるんでしょうか?
安藤 まずは、好きに作っていく感じです。その後、まだ曲がない、空いているステージのものをやっていくとか、わりと適当ですかね。
石川 安藤さんは、年をとるごとに作るスピードが速くなっているんですよね。私の担当分がどんどん少なくなっている(笑)。効果音については、ファイルの競合が起きると困るので、例えば"このボスは安藤さんやってね"とか、"カービィのこの能力の効果音は私がやります"とか、あらかじめ振り分けますね。
─シーンはどう意識して作っているのでしょうか? あるシーンは自分が作っていて、次のシーンは違う人ということがあり得るわけですよね?
石川 最近は、ディレクターの熊崎(信也)が、"今やっているのが終わったら、あの面を作って"とか言って走り去っていくので、それを信じて突っ走る感じです(笑)。昔は、自分で構成も考えていました。今回はこういう感じにしようとか、ラスボスに行く前だからこういう曲にしようとか、どうやってラスボスを意外で激しい曲にするかとか、全体を見ながら考えて作っていましたね。ところが熊崎ディレクターという人は、それを自分でやりたいし、できちゃう人なんですね。例えば、私がラスボス曲のつもりで、これ以上激しいものはない!と意気揚々と渡すと、それを最終面のレベル・マップに使っちゃうんです。何やっているんですか?って聞いたら、"これを聴いて当たり前に思った人が、びっくりするような曲を作ってください"と。これ以上は無理ですって言っても、"石川さんならできる"と笑っているんです(笑)。
安藤 だから、最近は作った曲がどこに使われるか分からないことが多いですね。ゲームがだんだん出来上がってくると、まだ曲がない場所に、こんなものを作ってくださいと、指定が具体的になってきて、それに合わせて作るようになりますね。
─逆に考えると、まだ何もないときに作る最初の曲は難しかったりしますか?
安藤 難しいというか、自由過ぎるというか。とりあえずどこかで使えるだろうって思って作ることもありますけど。
─そういう場合は、自分の中でテーマを設けたりするんでしょうか?
安藤 テーマらしきものがイメージできたらそれを最初に作りますが、本当に何も出ないときは、とにかく何かを作って、作っているうちに"この曲のこの部分をテーマにしたら面白いんじゃないか"と気が付いていく感じでしょうか。それにほかの作る曲を寄せていって、今回のテーマはコレだ!みたいに徐々に確信を持っていくっていう。やりながら考えるみたいな感じですね。
(続きはキーボード・マガジン2017年7月号 SUMMERにて!)

| 品種 | 雑誌 |
|---|---|
| 仕様 | A4変形判 / 184ページ / CD付き |
| 発売日 | 2017.06.09 |